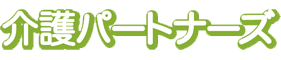日常生活上の支援だけでなく、リハビリに必要な機器が整備された施設で理学療法士などによるリハビリを受けることができる介護サービスが、デイケアと呼ばれる通所リハビリテーションです。
自宅から通いながら利用する点はデイサービスと似ていますが、サービスの内容など異なる点は色々あります。
そこで、デイケアではどのような介護サービスが提供されるのか、その内容を把握しておきましょう。
通いながら短時間でリハビリを受けてもらう施設
介護を必要とする方の中には、施設に入所している方以外に、自宅で普段生活を送りながら病院や診療所、施設などに通って日々の生活支援を受けたり、リハビリなどのサービスを利用する方もいます。
デイケアと呼ばれる通所リハビリテーションもその1つで、施設内には理学療養士や作業療養士、言語聴覚士といったリハビリの専門職の方が在籍している上に、備えられている機器も充実しており、安心してリハビリを受けることができます。
リハビリ専門の担当者以外に、看護師や介護士も常駐しているので、介護や医療、リハビリの専門の方たちがチームとなって利用者をサポートすることになります。
デイケア利用を希望する方の特徴
デイケアは、リハビリテーション病棟から退院したけれど、継続してリハビリを続けたいという方、長期的なリハビリが必要な方、認知症の方などが利用しています。
日常生活上のサポートはそれほど必要がないという場合には、リハビリを中心として1時間から利用可能となっているので、よりリハビリに専念しやすい施設ともいえるでしょう。
一般的にデイケアに在籍しているのは、医師は1人以上、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、介護職員は利用者10人に対し1人以上という数です。
実際にデイケアを利用できる方
デイケアを利用できるのは、要介護1~5の認定を受けている在宅で生活する方のうち、医師からリハビリテーションが必要だと判断された方です。
要支援1や2の認定を受けている在宅で生活する方は、同じデイケアでも「介護予防通所リハビリテーション」でサービスを受けることができます。

デイサービスと何が違う?
デイケアとデイサービス、どちらも通ってサービスを利用することになり、食事や入浴など日常生活を送る上で必要な支援を受けることができます。
また、デイサービスでも機能訓練を強化したリハビリ特化型や機能訓練特化型といった形のサービスも増えています。
ただ、デイケアは食事や入浴など日常生活の支援も行いますが、リハビリテーションを通した身体機能の維持・回復、認知機能改善がメインとなります。
デイサービスは人との交流の機会を持ち、社会的に孤立することから解消し、心身機能を維持・向上させることをメインとして行うため、方針そのものが異なるといえるでしょう。
機能訓練特化型やリハビリ特化型というデイサービスになると、デイサービスではありますが、午前または午後のみのサービス提供であったり、食事や入浴設備がないというケースもあるようです。
運営方針も異なる
デイケアは、主に病院や診療所、介護老人保健施設などがサービスを提供していることが多いので、施設内のリハビリ設備は十分整備されている点もデイサービスとの違いといえます。
さらに医師が1人以上必ず常勤しており、利用者それぞれに医師の指示書と運動機能検査などに基づいた計画書が作成されています。
デイサービスでも計画書は作成されますが、これは医師の指示書に基づいたものではないので、利用者の身体状況や生活環境、希望などを基準として自立を目指したサービス内容が決められます。
よりリハビリへの専門性が高いのはデイケア
デイケアには理学療法士をはじめとする、作業療法士や言語聴覚士などリハビリ専門のスタッフが設置されます。
デイサービスにも理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが設置されることもありますが、他にも看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格のある機能訓練指導員なので、必ずしも理学療法士などが施設内にいるとは限りません。
しかし、機能訓練型のデイサービスなら機能訓練がメインとなっているので、リハビリには理学療法士や作業療法士、看護師など専門スタッフによる支援を受けることができます。ただし3時間から4時間の利用時間となり、一般的なデイサービスよりも短い時間で介護予防に重点を置いた機能訓練を受けることが可能です。
デイケアとデイサービスは併用可能?
デイケアとデイサービス、どちらも併用したいという場合は利用者が受けている介護認定のレベルにより異なる点に注意しましょう。
介護保険では利用者の要介護度が高いほど利用できる介護サービスも増えます。要介護度1~5に認定されている方ならデイケアとデイサービスを併用することができますが、要支援1や2の認定を受けている方の場合、いずれか一方のサービスしか利用できません。
ただし、これらはどちらにも保険を適用させることができないだけで、いずれか利用者が全額負担するなら併用することも可能とされています。