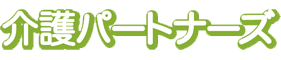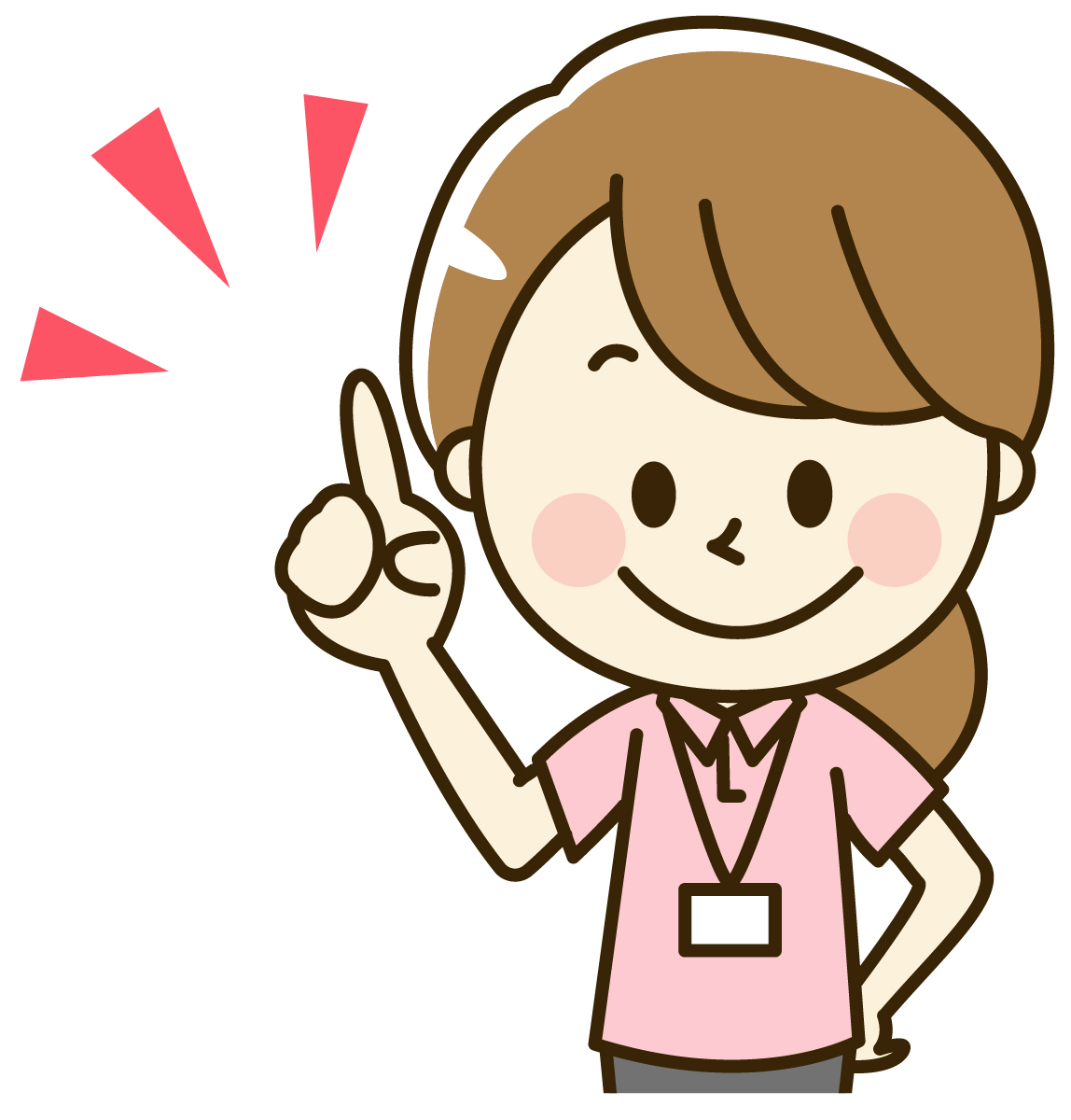目次[非表示]
介護業界で使われている「トランス」とは、たとえば利用者がベッドから車いすに移動するといった「移乗動作」のことです。
「トランスファー」を省略した言葉であり、「移動」や「乗り換え」といった意味の介護用語として使われています。
そこで、介護現場で欠かすことのできない「トランス介助」の具体的な方法と、介助のポイントについて説明していきます。
「トランス介助」の方法と7つの流れ
介護現場では「トランス介助」を行うタイミングが多く、たとえば利用者が車いすを使っていれば1日に何度もトランス介助が必要となります。
トランス介助は転倒するリスクも高いため、介護者は適切な介助方法を身につけておくことが必要です。
そこで、ベッドから車いすに移乗するときのトランス介助を例にして、その方法と次の7つの流れを説明していきます。
①車いすの準備
②ベッドに車いすを近づける
③利用者を立ち上がりやすい座位に整える
④利用者に車いすを近づける
⑤利用者と介護者が移乗介助の姿勢を取る
⑥声かけと移乗
⑦姿勢を安定させる
①車いすの準備
利用者の車いすを用意し、転倒を防ぐためにブレーキやフットレスト、アームサポートなどに異常がないか確認しましょう。
②ベッドに車いすを近づける
車いすをベッドへ近づけますが、注意したいのは車いすを置く場所です。
たとえば片側に麻痺のある利用者なら、車いすは麻痺のない側に近づけることが必要になります。
③利用者を立ち上がりやすい座位に整える
利用者が立ち上がりやすい座位に整え、安全に移乗できるようにしましょう。
まずは利用者の身体を支えながら、つま先が床につくまでベッドの高さを調節します。肩甲骨のあたりを支えて身体を密着させ、臀部を左右に浮かせながら身体を前へ引き出すように移動させてください。
④利用者に車いすを近づける
利用者にベッドのサイドバーを持ってもらい、転倒しないように車いすを微調整します。
座面と利用者の間にこぶし1個入る程度のスペースが開く位置に車いすを近づけます。

⑤利用者と介護者が移乗介助の姿勢を取る
利用者の手を介護者の肩にまわしてもらい、利用者の肩甲骨と骨盤を支えるように身体を密着させます。
介護者は足を利用者の軸足と車いすの延長線上に置く位置に広げておき、ひざを曲げて重心を低く保ちましょう。
⑥声かけと移乗
利用者に声かけしながらタイミングを合わせ、車いすへと移乗します。
前傾姿勢を取ってもらい「12の3」と声かけして移るとよいですが、利用者の身体を持ち上げようとせず、車いす側へ回転するイメージで移乗しましょう。
⑦姿勢を安定させる
かかとを浮かせない程度に利用者の足を引きながら前傾姿勢を促し、左右に体が傾かないようにします。
片麻痺などで身体が傾きがちなときには背中やひじにクッションをあて、姿勢を安定させるようにするとよいでしょう。
「トランス介助」を行う上で押さえておきたい3つのポイント
介護現場でトランス介助を行うとき、次の3つのポイントをそれぞれ意識しながら介助するようにしましょう。
- 「ボディメカニクス」を活用
- 車いすのブレーキとフットレストの確認を徹底
- 利用者に対する声かけは必須
「ボディメカニクス」を活用
トランス介助で活用したいのが「ボディメカニクス」です。
「ボディメカニクス」とは人間の動作による筋肉や関節の力学的関係を活用する方法で、理解を深めておくことにより介護者も利用者も余分な力をかけることなく、最小限の力でトランス介助することができます。
まず、足を肩幅に開き重心を低い姿勢に保つことが基本となり、介護者と利用者が身体を密着させ平行移動を心掛けることが必要です。
ボディメカニクスを活用したトランス介助により、介護者に見られがちな介護ケアによる腰痛を防ぐこともできるため、必ず取り入れていきたい方法といえます。
在宅介護を担当する利用者の家族も、ボディメカニクスによる介助は有効とされているため、特に身体的な負担が大きくなるトランス介助にはボディメカニクスを積極的に活用することを意識してください。
車いすのブレーキとフットレストの確認を徹底
転倒させずにうまくトランス介助を行うためには、車いすのブレーキやフットレストなどは常に確認してください。
事前確認で異常が見られなかったときでも、トランス介助の前に再度、ブレーキがしっかりかかっているか確認することが必要です。
トランス介助は毎日行うため、その介助や流れになれてしまうことなく、どれほど忙しいときでも必ずブレーキとフットレストはこまめに確認するように徹底してください。
利用者に対する声かけは必須
トランス介助は利用者と介護者がタイミングを合わせて行うことがポイントであり、声掛けは必須です。
ひとつひとつの動作の前に利用者に声かけをするようにし、安心して介護を任せてもらえるような配慮が必要といえます。