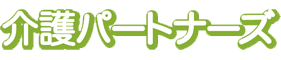目次[非表示]
介護現場には様々な専門職の方が働いていますが、ケアマネージャーもその1つです。
ケアマネージャーの正式名称は「介護支援専門員」といい、介護を必要とする要介護者が適切な介護サービスを利用するためのケアプランを作成することが主な仕事となります。
他にも自治体や介護事業者と利用者をつなぐ橋渡しのような役割を担うこともあるなど、介護サービス利用者にとって欠かせない存在です。
ケアマネージャーが行う主な仕事
ケアマネージャーが働く職場は、
- 居宅介護支援事業所
- 特別養護老人ホームなどの介護施設
- 地域包括支援センター
- 介護用具レンタル事業所
などです。
働く場所は異なる場合でも、主に次のような仕事を担当しています。
要介護認定に関する手続業務
介護保険を使って介護サービスを利用するためには、市区町村による介護の判定基準を満たし、要介護認定を受けなければなりません。
認定を受けるために必要な調査を行うこともケアマネージャーの仕事の1つです。
さらに要介護認定を受けた方の自宅を訪問し、心身状態など確認しながら更新手続に必要な書類を作成することもあります。
ケアプランの作成
介護計画書のことをケアプランといいますが、作成はケアマネージャーが担当します。
介護を必要とする方がどのようなサービスを受ければ、自立した生活を送ることができるのか分析し作成していきます。
要介護者のケアプランは民間の居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーが作成しますが、要支援者の介護予防に対するケアプランは地域包括支援センターのケアマネージャーが作成します。
給付管理
介護保険を使った介護サービスを利用すると、介護給付費の管理が必要です。介護事業所によっては事務担当者が行うこともありますが、この給付管理は基本的にケアマネージャーの仕事です。
介護保険が適用され介護事業所に介護給付金が支払われるように、毎月請求に必要となる書類を作成し、国民健康保険団体連合会へ提出する業務を担います。
利用者やその家族からの相談業務
要介護者が介護事業者に対し伝えたい要望がある場合や、改善してほしいと感じていることがあっても、直接伝えることは難しいこともあります。
その場合、ケアマネージャーが調整役として間に入り、利用者と介護事業者双方の意見を代弁して伝えることも行います。
ケアマネージャーのメインともいえるケアプラン作成の方法とは
介護事業者は、ケアマネージャーにより作成されたケアプランに従った内容のサービスを提供します。
ケアプランとは利用者がどのようなサービスを受けるか決めた介護計画書のことで、要介護者と要支援者のどちらにも必要となるため、要介護者はケアプランを、要支援者は介護予防ケアプランを作成することになります。
ケアマネージャーが利用者の状態を把握し、どのサービスを受ければよいか見極め、提供する介護事業者を選び利用するサービスと組み合わせ原案を作成していきます。
その上で実際に利用者と検討しながら、ケアプランを完成させていくのが一般的な作成までの流れです。
①利用者と面談
ケアマネージャーは、まず利用者の心身状態を把握しなければどの介護サービスが必要か判断できません。
そして利用者本人とその家族が、どのような生活を望んでおり、不足する部分や障壁になっていることは何かサービスを利用することで解決できる問題を洗い出す必要があります。
そこで、利用者と面談した上で状態を確認し、必要なサービスを決めていくことになりますが、ケアマネージャー独自の判断をしないように厚生労働省の「課題分析標準項目」を用いて実施されます。
②介護サービス提供事業者に照会をかける
利用者が必要とする介護サービスが決まったら、そのサービスを提供している介護事業者を照会し、
- サービスの種類やその内容
- 利用する回数
- 利用する時間
- 料金
などをまとめます。
③原案を見直す
原案として作成したケアプランが、本人とその家族の希望に沿うものになっているか確認と見直しも行います。
特に問題がなければ、介護事業者の担当者や主治医などの関係者を集め、「サービス担当者会議」によりケアプランを完成させます。
④契約
完成したケアプランの内容で本人やその家族が納得したら、同意を得た上で利用者と介護事業者が契約を結び、サービスの提供が開始されます。
ケアマネジメントの枠に収まらない業務内容
ケアマネージャーは利用者に対しケアプランを作成したら終わりではなく、定期的に利用者を訪問し最適なケアプランとなるように見直しを行います。
そのため介護事業者と連絡を継続して取り、提供されているサービスに不満や不都合など起きていないか確認することも必要です。
ときには介護事業者と利用者との仲介役として、その仲を取り持つといったことも行いますし、地域活動へ参加するように促すといったことも行います。