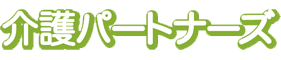実際に介護現場で働く方の中には、高齢者の生活に寄り添いながらサービスを提供することにやりがいを感じている方も少なくありません。
しかし介護の仕事は3Kなどマイナスのイメージが強く、若い世代などにも敬遠されがちで人手不足の状態です。
そこで、そもそも3Kとはどのようなことをあらわしているのか、マイナスのイメージが強くなっている理由をご説明します。
介護のイメージで持たれやすい「3K」とは?
介護業界以外にも、「3K」と呼ばれる職種はいろいろあります。
そもそも「3K」とは、きつい・汚い・危険をイメージさせる労働条件の厳しい状態をあらわす言葉です。
介護職が3Kといわれるのは、
・体力や精神面でのきつさ
・汚物に触れる機会の多さ
・危険な病気への感染リスク
などで、きつい・汚い・危険を連想させていると考えられます。
さらに介護職の場合、3Kではなく「給料が安い」というイメージを加えた「4K」であると考える方もいるほどです。
実際、大変な労働であるのに賃金が他業種より安く、賞与もないケースもめずらしくないため、見合わない給料と考えられることもあります。
給料は介護事業者や勤続年数などにより異なるため一概には言えませんが、仕事量に見合う給料を受け取ることができないと感じる介護職員は多いようです。
実際、短期間で辞めてしまう介護職員も多く、定着率の低さも問題となっています。

介護職が「3K」と呼ばれる背景
実際、介護職のどこが「3K」の原因となっているのか、体力や精神面でのきつさ・汚物に触れる機会の多さ・危険な病気への感染リスクといったそれぞれの内容を考えてみましょう。
体力や精神面でのきつさ
介護現場では、身体的な機能が低下している方や寝たきりの方、車いすの利用が日常必要な方などを抱えたり移乗させたりしなければなりません。
その際、腰を痛めてしまう介護職員もいれば、体力的に限界を感じてしまうといったこともあります。
また、介護施設によっては24時間365日稼働状態となるため、夜勤などもあり変則的な勤務の時間帯に慣れず体調を崩すこともあるでしょう。
汚物に触れる機会の多さ
介護現場での排せつ介助では、おむつ交換も必要ですし、排せつのサポートも行うこととなります。
食事介助においても、どの利用者の方もうまく食べ物を口に運べるわけではないため、食べこぼしなどもあるでしょうしうまく飲み込むことができず吐き出してしまう方もいます。
危険な病気への感染リスク
抵抗力の弱い高齢者が生活する施設では、ノロウィルスやインフルエンザなどの集団感染が発生しやすくなります。
特に今は新型コロナウイルス感染症など、従来までにはなかったウイルスへの感染も懸念される状態です。
たとえコロナ禍でもリモートワークで対応できる仕事ではないため、感染リスクなど不安な状態のまま働かなければなりません。
介護サービスを提供するためには、直接利用者に触れたり至近距離で接したりすることも避けることができず、ソーシャルディスタンスを保つことはできないといえるでしょう。
また、重い病状や障がいの程度の方の介助で、介護職員が転倒や転落してしまうケガのリスクもあります。
介護の仕事への対応策を検討することも必要
介護は3Kのイメージが強いのは、高齢者が生活を送る上で欠かせない部分をサービスとして提供する仕事だからですが、イメージを払拭するなら対応策も必要となります。
たとえば次のような対応策を行い、介護の仕事に対する捉え方を変えていくといったことも必要です。
・きつい…身体的な負担が重くなっているのなら、介護職員が適切な介助方法を学ぶことや、介護用ロボットの活用などで軽減することも可能
・汚い…排せつ介助などの業務が難しい場合は、直接利用者に触れることのない業務の仕事を希望してもらう
・危険…労災の指標である死傷年千人率を見ると、一概に介護の仕事が突出しリスクが高いわけではないものの、感染リスクは徹底して行うことが必要
介護ロボットやICTの導入で負担は軽減される?
近年、介護業界でも介護職員の身体的な負担を軽減させるために、介護ロボットを導入することやICT化などが進んでいます。
特に介護ロボットは、装着型パワーアシスト・歩行アシストカート・自動排せつ処理装置・認知症利用者の見守りなど様々な機能を備えており、利用者の自立支援や介護職員の負担軽減に役立っています。
介護現場の職員数は、高齢者の数に対して不足している状態であるため、今後も介護ロボットが現場に普及されていくことが期待されています。
様々な介護ロボットの開発は進んでいますが、一般的に十分普及しているとはいえず、約7割以上の介護現場で介護ロボットは導入されていません。
まだ人が操作しなければならない部分も多く、中小の介護事業者などは資金面で設備投資が難しいといった課題も残っています。
それでも介護ロボットの利用を希望する介護事業者も多いため、今後は普及していく可能性が高いといえるでしょう。